Newsletters
 DIDI Newsletter (2024年3月29日 公開)
DIDI Newsletter (2024年3月29日 公開)
2024.3.29
DIDIは3年の区切りを迎えます。最終号では、2年半にわたりセンター長を務められた尾方義人先生に、DIDIでの3年間を振り返ってもらいました。
DIDIの3年間で感じたこと
−尾方先生はデザインが専門ですが、どのような研究をされているのでしょう。
もともとは工業デザインの現場で、製品のデザインやグラフィックデザインなど、実際に使われるものを作ってきました。大学では実践のみならず、デザイン学として大きな方法論にしていくことを基本的なスタンスとして、デザインしたものを何か別の成果につなげよう、何か社会につなげようというような方法論や教育方法を研究しています。
−DIDIでの3年間は、先生にとってどのようなものでしたか。
そもそも私は社会学や障害学の専門ではありません。先ほど話したように現場仕事をたくさんしていた経験があったこと、またちょうど改組で未来構想デザインコースという新しい教育や未来構想デザインコースのコンセプトを谷正和先生(九州大学大学院芸術工学院 前研究院長)と話していたタイミングでもあり、DIDIの立ち上げからメンバーになりました。
工業デザインの場合、期限までに製品を作ること、そして買ったり使ったりする人たちにとって問題ないものを作ることが大前提です。社会包摂デザインにもそのような部分はあるものの、むしろ対象に対してどうしていくかをずっと考え続けないといけないもので、心がけるポイントが工業デザインとは少し違っているので、私にとっても勉強になった3年間でした。
なかでも、様々な分野の先生方とプロジェクトを共有することで、私に今までぜんぜんなかったボキャブラリーがセンターを通じてどんどん増えていき勉強になったという実感がとてもあります。
−違うアプローチが見えたということでしょうか。
同じ目的や解決に向けて「なるほどこんな見方をするのか」「こんな方法があるのか」という感じでした。DIDIにはもともと私と違う方法論の先生が多くいらっしゃるのですが、そういった方々とやりとりをしていくことはとても面白かったです。例えば、2年目にリーガルデザインディクショナリーに取り組むきっかけになったのは田中先生がいたからです。田中先生が、私が書いていたコラムを読んでリーガルや仕組みの切り口でボキャブラリーを抽出してくれて、この方法はいいなと思い至りました。
―今のお話をうかがうと、DIDIは様々な専門分野のメンバーで構成されたことで、研究の多様性が見出せたのかと感じました。
先生たちはみな忙しいこともあって時間を合わせるのは難しく、一緒に何か新しいプロジェクトをやっていくことは、そう多くはありませんでした。ですが何かを一緒にやることはなくても、同じ組織にいることで「この先生はこんなことを、こんな方法論でやっているんだ」というようにお互いの活動が見えやすかったし、研究会の企画を見ていくだけでもとても意義深いものがありました。
須長先生のような視点で、ある程度の定義をしてもらうことも、とても大切だと感じました。
―DIDIには様々な専門の先生たちがいて、やり方も考え方も千差万別。どれが良い悪いではなく、いろいろなやり方やアプローチの仕方があり、それをお互いに知ることができるのもDIDIの一つの大きな特徴かと思います。
観察の仕方はみな近いものがあったんですが、観察したことをどう分析していくか解釈していくかは研究によってぜんぜん違ったりすることを実感しました。ほかの先生たちのプロジェクトの進め方を見ていくことで、お互いの違いを共有あるいは認識し、逆に自分の立ち位置や方法がよりはっきりしてくるのを私は感じましたし、それぞれの先生もそのような捉え方をされているように思います。
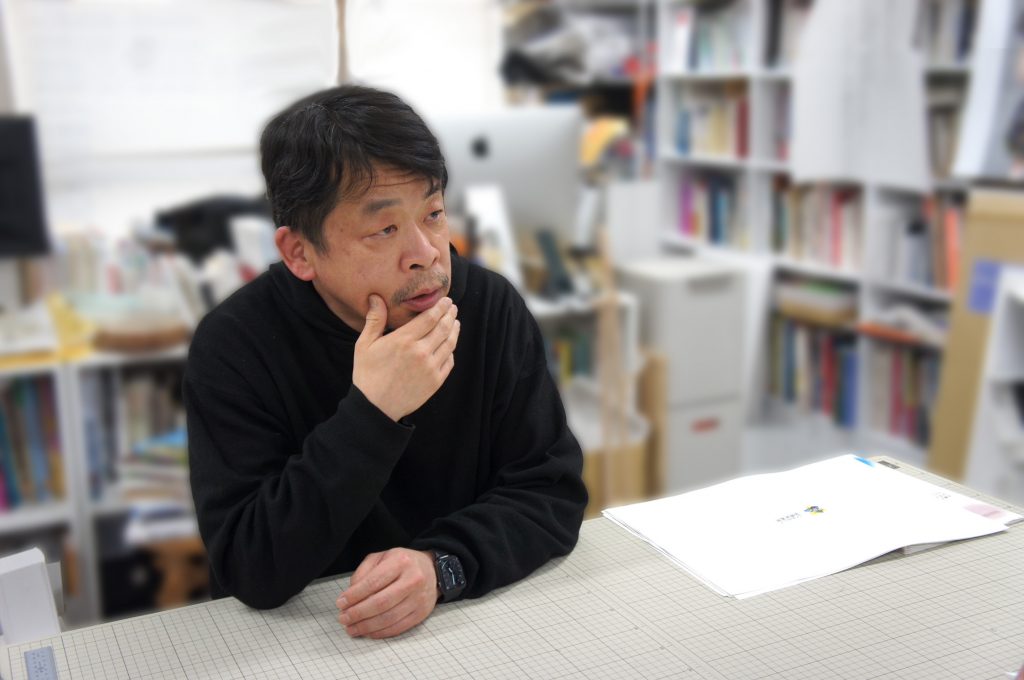
DIDIでのプロジェクトや教育を通して見えてきたこと
―先生がDIDIで行った主なプロジェクトは「ジェンダー/LGBTsのデザイン」であり、また「ジェンダーデザイン・コンテスト」も中心で活動されていました。
私はジェンダーの専門では全くないので、多くの先生や現場の人たちに話を聞き、学生と考えました。「ジェンダー/LGBTsのデザイン」ではジェンダーそのものではなく、ジェンダーが持つ問題に対してどのようなデザインのアプローチができるかをやっていきましたが、いつの間にか学生たちが自主的に展覧会をやりたがるようになり、参加する学生も明らかに増えていきました。展覧会の作品にしてもコンテストのポスターにしても、おそらく学生たちは「デザイナーのアプローチでジェンダーに関するいろいろな表現ができるんだ、やっていいんだ」と感じ、参加してくれたのではないでしょうか。
―ジェンダーが持つ問題について頭でガチガチに考えるのではなく、作品やポスターを通すことで自然とスッと考えられる、入っていくように私も感じました。
工業デザインの話に戻ると、最初から「これはとても素晴らしい技術です」と説明しても誰も買ってくれません。第一印象が良くないとまず第一歩が始まりませんから、やっぱり表現とかコミュニケーションをしていくことから始めるのが肝心です。ですから「ジェンダー/LGBTsのデザイン」「ジェンダーデザイン・コンテスト」では、人権に関わる難しいものでも、表現を大切にしたところにとっつきやすさを持ってもらえたように思います。
―「ジェンダー/LGBTsのデザイン」はこの3年で終わりでしょうか。あるいは次の構想はありますか。
ジェンダーからもう少し広がり、婚姻制度を軽やかに深く考えるための展示会やワークショップ、婚姻届デザインをリデザインするなど発信していきたいとも思います。来年度(2024年度)やってほしいとの依頼をいただいています。自治体との連携事業の最初の展示は福岡市男女共同参画推進センター・アミカスでやったのですが、それをほかの自治体の方が見られて「うちでもできませんか?」というように、連鎖するというか継続してやっていっている感じです。
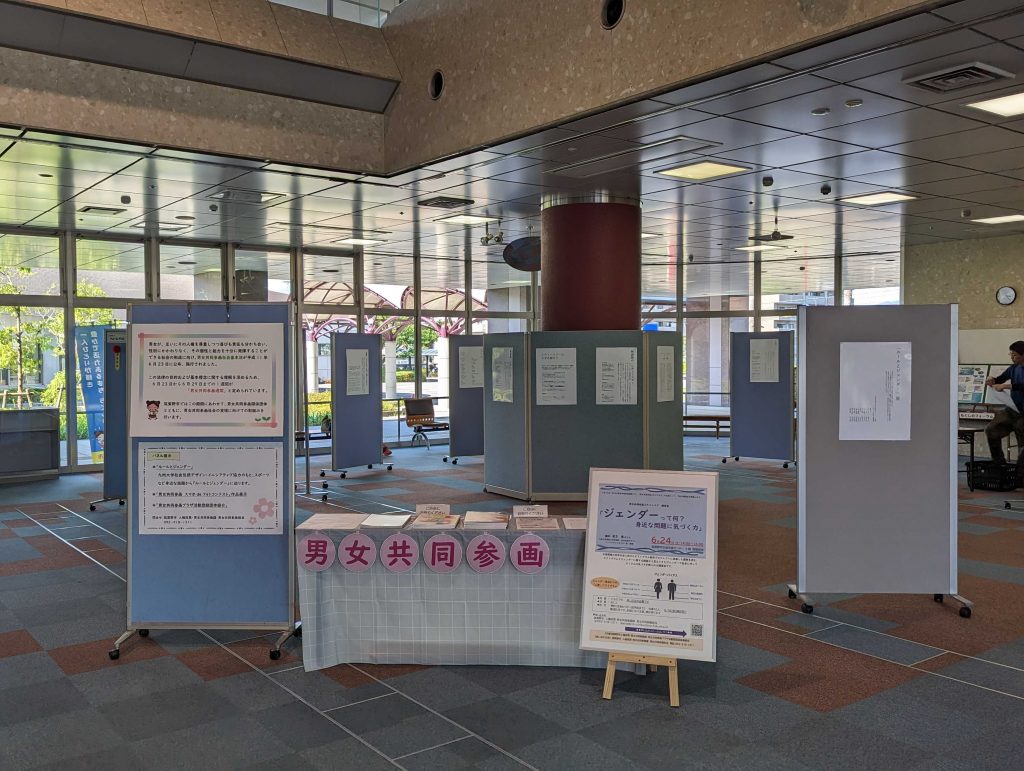
「ルールとジェンダー展」



―教育面でも、DIDIは様々な授業にも取り組まれました。
授業のパターンは大きく二つありました。一つは朝廣和夫先生や長津結一郎先生がやっている「半農半アート」のような、すでにある現場において、学生に関わってもらって経験値を上げていくような授業です。もう一つはちょっと抽象的なんですがソフトとデザインという考えで、いろいろな事例と方法論を詰め込み型でやっていく「社会包摂とデザイン」という授業です。これは教員も学生も、学科も違えば専門も違っていて、でも社会包摂という軸で話をしていくというパターンのものでした。後者は、意外にも学生の反応が大きくて、どの学部の学生もまんべんなく受講してくれましたね。先生もいろいろいれば、学生もいろいろいるという、ある程度想定はしていましたがこんなにも幅広くなるとは思っていませんでした。
―いろいろな分野の学生たちが興味を持つこと自体、ポテンシャルがあるなと感じます。
学部2年生以上の学生が受けられる授業ですが、授業が終わった後も相談の連絡をくれる学生が毎年数人います。工学部、理学部、医学部、文学部のように伝統的な体系は大学において絶対に必要ですが、それとは別に芸術工学部みたいな違うディレクトリがあることは重要な気がしましたし、また芸術工学部以外にも社会包摂を勉強したい学生がたくさんいることも実感しました。
―高校生を対象にした講座もされていましたが、大学入学の手前の世代からアプローチするなどの理由でしょうか。
アプローチする場合もありますが、オープンキャンパスのときに社会包摂の説明を聞いた高校生から直接、連絡をもらったこともありました。昨年の長崎県の高校の生徒さんがその一例です。長崎のご当地キャラクターがジェンダー問題で物議を醸したことについて考えたいので何かアドバイスをしてもらえないかとの相談を受けました。忙しい中ですが大事なことなので優先して時間を取りました。
「ジェンダーデザイン・コンテスト」でも感じたのですが、現在の10代の人たちはもうジェンダーや男女共同参画に関してネイティブで、そういったことへの意識を自然に持つようになってきています。SDGsや環境問題もそうですよね。先日、高校生を個別で指導する機会があったのですが、その学生が「SDGsや社会問題に対して、やってますよ感を出しているところが多すぎないですか?」と話していたのは強く印象的に残っています。
―若い人たちの感覚が変わってきている今、これからの日本に期待を持ちたくなるお話です。この流れから、2024年度に公開が予定されている新たな教育プログラム構想について聞かせてください。
既存のカリキュラムマップとは異なる枠組みの授業群を構築する計画を立てているところです。例えば、いま芸術工学部やインクルージョン支援室が取り組んでいるようなユニバーサルデザインやジェンダーに関わる授業、また福祉に関わる授業を一定の単位数以上受けるとプログラム認定される。つまり、他学部のこの科目と芸術工学部のこの科目を受講すると社会包摂デザインを勉強したことになるといったものを考えています。
―より社会包摂デザインを考えていくためのシステムのようなものでしょうか。
そうですね。今は2単位だけなんですけど、5から7単位ぐらいの枠にするともう少し体系的な勉強ができると企画しているところです。
―この3年の間に社会包摂の理解が徐々に広がっているように思います。いきなりガラリと変わることはもちろんないとしても、世の中が少しずつ変わってきていると感じる部分はありますか。
そうですね、時代的なところはものすごい勢いで変わってきている気はします。ただ社会は変わろうとしていますが、やっぱり概念や方法はまだ追い付いてないような気がするので、DIDIで取り組んでいるような研究や教育はこれからも引き続き必要だと思います。
尾方先生からのおすすめ本
尾方先生から、「設計・デザインの学校である芸術工学部の先生にぜひとも読んでもらいたい本です」と、3冊紹介してもらいました。
「図説 デザインの歴史」
どの分野デザインにおいても、歴史的史実や過去の経験に基づいています。私達が今まったく新しいことを考えることは大変難しいです。過去のデザインの方法や概念を獲得するためには、デザイン史の勉強が最も早く、効率的です。
実践的な領域のデザインの方法について、網羅的に書かれた書籍です。概念的でなく抽象的でなく、実践デザイン・デザインの研究双方に参考になる書籍です。重要な語彙や方法論がわかりやすく、使える方法として説明してくれています。
理論のための理論でない実践的な教育や研究に基づいた書籍です。若干翻訳がわかりにくいところもありますが、デザイン研究へのアプローチや授業課題の論理的背景構築のために十分参考になります。
<プロフィール>

尾方 義人(おがた よしと)
九州大学
大学院芸術工学研究院 未来共生デザイン部門 教授
総長補佐
【大学院(学府)担当】
芸術工学府 芸術工学専攻 未来共生デザインコース
【学部担当】
芸術工学部 芸術工学科 未来構想デザインコース
芸術工学部 工業設計学科
通信機器・家電・家具・計測機器・医療機器などのインダストリアルデザイン・プロダクトデザインの実践を行い、そこからデザイン実践のための概念と方法の構築を目指している。また、領域にとらわれないデザイン対象と分断されない「デザイン実践」と「デザイン理論」の構築を目指し、デザインの過程や手法を循環する「カ・カタ・カタチ・カチ」として捉え、人間のための「モノ」のデザインを積み重ねることで、よりよいモノづくりを考えている。このような工業デザインの教育・研究に基づき、未来構想デザイン・スペキュラティブデザイン・レジリエンスデザイン・デザイン方法史を新たに進めている。
